
2月になって寒い日が続きます。このような季節になると、どうも体が重くなったり疲れたりしませんか。つい「トシだしなあ」とぼやいてしまいますよね。しかし毎年この時期、体が疲れたり体調が落ちたりするのは年齢のせいだけではないようです。その原因の一つが「寒暖差」です。今回はその原因を探ってみました。
●冬の寒暖差は体調不良を起こす
今年は年明けから寒い日が続きました。
そこで室内ではエアコンやストーブなどの暖房器具を使って部屋を暖めます。室温は26℃くらいで一定ですが、寒波になると外気がかなり低くなります。
すると室内と屋外の寒暖差が大きくなります。このような状況で出入りを繰り返すと、負担が掛かって自律神経が乱れて体調不良を起こすのです。
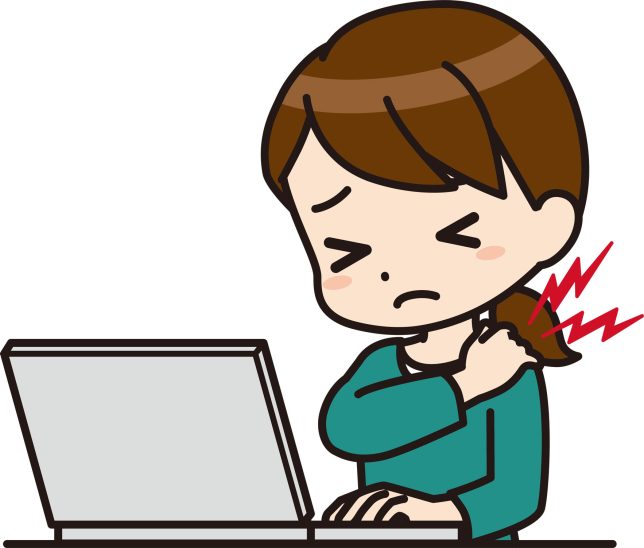
エアコンに例えて言うと、「暖房」スイッチと「冷房」スイッチを交互に切り替えるイメージでしょうか。
すると機械に負担が掛かりますよね。そしてトラブルが起こるわけです。それと同じです。
人間も「寒」⇔「暖」と頻繁に繰り返しますと、体はその都度体温調節を強いられて、ついには疲れてダウンしてしまうのです。これが不調の原因で、寒暖差疲労です。
●寒暖差による症状は
寒暖差による症状は、肩こり、腰痛、頭痛、めまい、不眠などが代表格です。
また体調的には体がだるい、気分が落ち込む、物事を楽しめない、集中力が続かない、ヤル気がでないなど気分の変調などがあります。
ただ病気という程でもないので、大半の人は「調子が悪いなあ」と思いながら過ごしているようです。

この原因は自律神経の失調です。
体質的にその働きの強い人はあまり寒暖差の影響は受けません。
しかし体質的に働きが弱い人は寒暖差の影響を受けて症状(つまり不定愁訴)が出るようです。
また年齢的には若い人は体力がありますから、その影響を受けにくく、また中高年以上は働きが鈍くなりますので、影響を受けやすくなるようです。
そもそも自律神経は汗をかく事で鍛えられます。
しかし去年は自粛生活で外で汗をかく機会が少なく、自律神経を鍛えることが出来ませんでした。更に慣れない在宅ワークのストレスで、自律神経を調整する力も低下しています。
そのような事から、この冬は寒暖差による不定愁訴が現れやすくなるんですね。
ではどうすれば良いのでしょうか。
